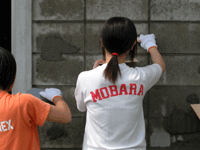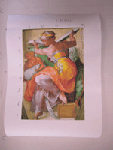 |
原画の用意
ミケランジェロのシスティーナ礼拝堂の壁画からもらいます。拡大が必要なので、原画と下絵に升目を作ります。さらに対角線を取り、形を追いやすくします。 |
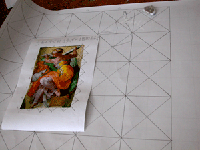 |
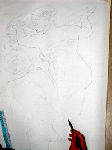 |
下絵はこの後、穴をあけて壁に転写します。この下絵をカルトンと呼びます。 | |
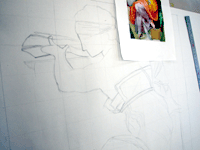 |
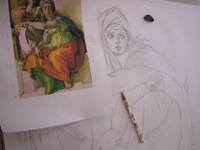 |
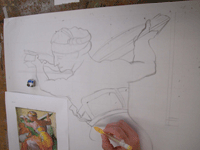 |
 |
床で作業したり、机で作業したり、自分のやりやすい方法で。2時間で終わらない人は宿題にしました。次回は壁を作って、転写をする予定です。 | |
 |
 |
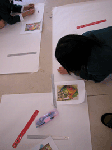 |
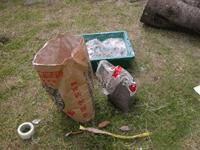 |
||||
| 石灰と砂。
砂はホームセンターで洗い砂を一袋購入しましたが、全然足りませんでした。急遽、鉄棒の砂場から拝借。洗って使うべきでしたが、下塗りなので可としました。砂の目が細かく、生徒には塗りやすかったようですが、ゴミや枯れ草が混じっていて一緒に練り込んでしまいました。 |
||||
 |
||||
| 練り
水を加えて、鍬で練り上げます。これが結構な重労働です。 左の鍬は、実は庭掃除用の草取り用の鍬、左側は畑仕事用のもの。チョッと使いにくいのですが、我慢、我慢。 |
||||
 |
||||
| 練り終わり
ふねがちょっと小さく使いにくく、もっと大きなものにすれば良かったと後悔しました。 |
||||
| 練り終わり拡大
水の分量は、砂の含水量との関係できっちり量れずいい案配でやめます。ちょうど良い堅さは耳たぶの感じだと聞いたことがあります。加水していくとは或る一定のところで急激に緩くなります。 左官屋さんの使うモルタルは垂れてくるくらい柔らかいのですが、それは作業効率を優先させ、亀裂ぎりぎりのところまで緩めるからでしょう。 フレスコで使うモルタルはそれに比べ固めです。 |
||||
 |
||||
 |
||||
| 左官ブラシで壁面を充分に濡らします。 | ||||
 |
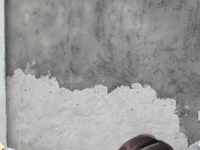 |
|||
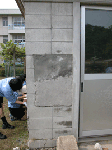 |
||||
| 常識的には下から上の方向に塗るのでしょうか。
コテの使い方も難しいようです。先の尖った方を使って平にしようとする傾向があります。コテの腹を使ってモルタルを拡げる感じなのですが。まあ、習うより慣れろということですね。 |
||||
 |
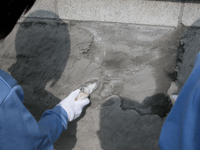 |
|||
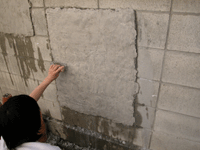 |
塗り終わり
2時間でだいたい塗り終えました。ここで、カルトンの転写をすべきでしたが、タイムアウト!。転写は次週に持ち越しです。そのため、カルトンの下書きは毎回移さなければならなくなりました。初めに塗ったところはもう描写できる状態で、転写をしておけばずっと残ったのですが。下絵の穴開けも未だなので仕方ありません。フレスコの制作は作業の分配と時間との戦いだと実感しました。 石灰は一袋のおよそ3/4を使いました。 |
|||
| 戻る | ||||
 |
||||
| 雨のため室内の作業。今年は天気が悪いようで関東地方はもう、11日も晴天がないそうです。
下に段ボールを敷き上から千枚通しで形にそって穴を空けていきます。 |
||||
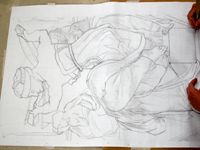 |
||||
| ひたすら、穴を空けていきます。 | ||||
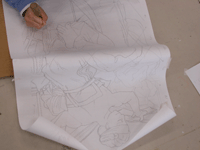 |
||||
| 画面が大きかったので、思った以上に時間がかかりました。2時間も穴空けをしてると手が腱鞘炎になりそうだと。音楽をかけて適当に休みながらやります。 | ||||
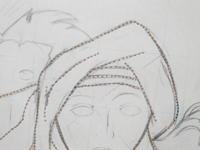 |
||||
| 拡大
穴の間隔は広過ぎず、狭過ぎず。点が大きくなると形の込み入った場所は判別不能になります。反対に小さくてもになっても同じです。切り取られない程度でしょうか。形の目安を移すことが目的です。 |
||||
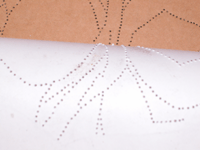 |
||||
| めっくて見るとこんな具合です。 | ||||
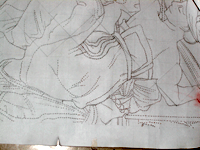 |
||||
| すべて穴あけ完了! | ||||
 |
||||
| 顔料(酸化第二鉄)をガーゼで包みます。これをカルトンの上からはたくと、穴を通って顔料が点線となって壁に付きます。 | ||||
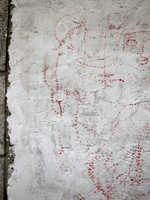 |
||||
| 次週は壁に転写して、上塗り、描画に入ります。 | ||||
| 戻る | ||||