 |
カルトンの上から顔料を入れた布袋を軽く叩きます。
「中塗り壁が既に乾いている時にはスタッコを充分湿らせ、顔料に石灰を加える」(丹波洋介フレスコ画の制作)べきでしたが、そのままでも下地の凹に入り込んで、色は残ります。また、テールベルトやローシェンナなどの土性の地味な色が後の描写に影響を与えずよいとされていますが、今回の制作では模写で形を追うことや全体の色調からライトレッドを選択しました。 |
 |
下からゆっくりめくります。 |
 |
ばっちり、写っています。 |
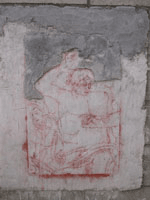 |
ジョルナータ(一日の仕事分)を上塗りします。
基本は、絵の上から。絵の具や削りカスが下に落ちて絵がよごれないようにするためです。しかし、そこは絵と相談してやり易いところから行うことにします。 |
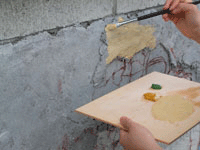 |
彩色
顔料は予め水練りしておきます。筆は豚毛の使い古し。細部の描写には面相や彩色筆を使う予定です。 |
 |
 |
 |
時間があまりないので、背景の単調な部分から始めます。
スタッコに絵の具が吸い込まれるように壁に付いていきます。上へ上へと色が重なりますが、パステルのように下の色が容易に動くことはありません。 |
 |
|
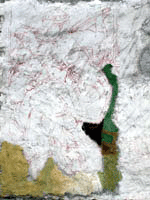 |
 |
| 戻る |
 |
先週はここまで進みました。 |
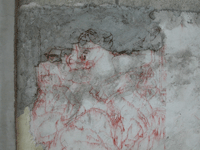 |
ジョルナータを上塗りします。
上塗りで隠れた下絵は、もう一度カルトンを当てて上から顔料を叩き転写します。 授業時間内に終わらせるためには、上塗りの後すぐに描き始めなければなりません。そのため、下地に与える水分は極力少なくし、また、上塗りのモルタルもかなり硬めにします。硬めのモルタルは塗りにくく、平面を作るのが困難でかなり不利です。凹凸が激しいと描画にも響きますが、我慢します。 |
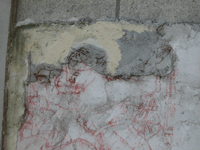 |
描写します。 下地が灰色でガサガサしているせいでしょうか、生徒は絵の具を盛り上げてします傾向があります。絵の具が厚みを持っても結構大丈夫ですが、目的の色を一発で決めるくらいの潔さが必要です。色の境目をぼかすと容易にグラデーションが作れます。上に載せる色は滲まずそのまま、下色の上に不透明に被ります。下色を動かして上色と混ざらないよう、色が濁らないように注意します。絵の具の濃さはこれも、いい加減が必要で、うまく、調整します。 |
 |
孤独に浸ってひたすら描きます。2時間のなかで、実際に描写できるのは40~50分ぐらいでしょうか。 |
 |
パレットの作り方はこちら。 |
 |
窯場の周りも新緑が。こういう気持ちの良い日は屋外の作業が最高です。真夏になる前に終わらせられればいいのですが。 |
| 戻る |
| 6月10日 | 保護者面談週間のため授業なし。 |
| 6月17日(雨天のため中止) | テンペラの下地づくりをしました。 |
 |
木の枝に雨粒が。
生憎の雨でしたが、小雨決行。 かんかん照りもつらいですが、 雨はもっと困ります。傘をさしたりしながらの制作になりました。 |
|
 |
 |
作例(Kさん)
この日の始まりと終わり 服の皺に苦労していました。 |
 |
 |
作例(Yさん)
予定どおりの仕事でした。足の形がうまく作れなく苦労していました。 |
 |
 |
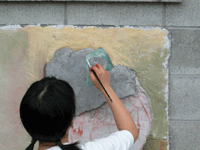
作例(Mさん)この日描き終えられなかった部分(腕から下)のスタッコは落としました。顔が別人? |
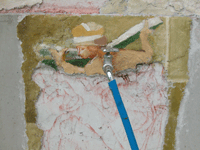 |
(Mさん)
画面のまんなかに水道の蛇口がオシャレです。雨で早々に退散です。 |
|
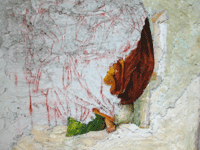 |
(Oさん)描写力のある生徒なので、徹底的に細部まで描かせます。壁がどんどん絵の具を吸ってくれるので、描き味に感動していました。 | |
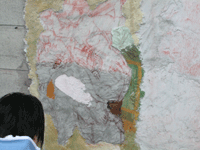 |
 |
 |
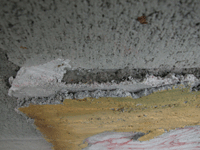 |
上から見たところ。
ロック壁、セメントモルタル、下塗り、上塗りの層が分かります。 |
|
 |
放課後の延長戦を終えたところです。1学期中に終える目処を立てたいのですが。 |
 |
 |
今日も雨。
青シートを掛け、傘を差しての制作になりました。放課後には雨も上がり、残って制作しました。そのおかげでずいぶん進みましたが、実は今回で1学期の授業は終わりです。残りは放課後に少しずつ進めます。 |
 |
 |
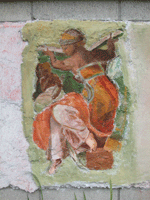 |
 |
 |
|
 |
 |
翌日の様子。遠くから見ると結構出来上がってきました。 |